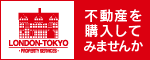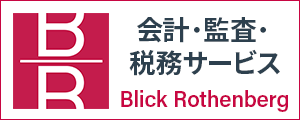第32回 緑色の国、茶色の国。
私が住むロンドンの西部地域で、自治体からゴミの分別収集用バッグが配られてきた。ペットボトルや空き缶などは白色、切った庭木や雑草などはピンク色だ。一部の先行実施地域に続き、ロンドンも分別時代に入ったようだ。日本では当たり前だったが、分別してゴミを出すのも久しぶりである。
それにしても「環境」という言葉は、ずいぶん語感が柔らかいな、と思う。色にすれば、緑色。日欧米の先進諸国では、「環境」は「緑」「グリーン」と完全に結びつき、すっかり良いイメージになった。そして同時に、茶色や黒色の印象が付きまとう「公害」という言葉が、日本では、すっかり忘れ去られてしまった。
小欄で何度も書いたように、私の実家は高知県高知市にある。
かつて、実家から100メートルほどしか離れていない場所に、大きなパルプ工場があった。煙突からは、亜硫酸ガスを含んだ煙が昼夜を問わず流れ出し、悪天候の日は低く垂れ込んだ煙が住宅街をはい回った。
廃液はもっとひどかった。パルプ工場は、ひどい悪臭を伴った、茶色と黒色が混じったような廃液を出す。煙と同様、垂れ流しである。すぐ近くを流れていた幅5メートルほどの川は常に流れが茶色で、透明度はゼロだった。魚も水草も皆無である。川は下流に行くにつれて幅広になったが、どこまで行っても、深い茶色が薄まることはなかった。この「江ノ口川」は当時、日本で一番汚染された川と言われていたという。
江ノ口川を舞台に、全国に知られた「生コン事件」が起きたのは、1971年6月である。私は小学校5年生で、日本はまだ高度成長期の真っただ中にあった。
その日、近所では早朝から大人たちが大騒ぎだった。パルプ工場の廃液が道路にあふれ、路面電車が走る国道も茶色の水に覆われているのだという。
私も急いで外に出た。自宅前の小路はふだんと変わりないが、すぐ先の広い通りでは、廃液が地面をぬらしている。朝もやが残っているような時間帯だ。太陽の光は妙に鈍く、自分の影はぬれた路面に長く伸びていた記憶がある。もっと早い時間には、廃液は足首を浸すほどの量だったらしい。大人たちの人垣を縫って前に進み、腕と腕の間から首を出すと、警察官の姿も見えた。
事件は、廃液のあまりのひどさに怒った住民の実力行使だった。垂れ流しを何とかしろと何度言っても、工場は耳を貸さない。行政も耳を貸さない。「それならば」と、大人2人が深夜、廃液口のマンホールの蓋を開け、生コンを流し込んだのだ。工場は24時間操業である。川への排出を遮られた廃液は、工場敷地内にあふれ、近所の道路も覆った。
2人は威力業務妨害容疑ですぐ逮捕された。もとより、逮捕覚悟の実力行使だったのだ。それでも、近所の人たちが「あの人らあ、ようやった」と、その気概を褒めたたえていたことを私は忘れていない。実際、2人を裁く法廷は、公害問題の象徴となり、支援者は全国に広がった。裁判ではその後、罰金刑が確定したが、地域の人々だけでなく、2人はある意味、全国でも共感を持って迎えられたのだと思う。
日本はそんな時代の中にあった。
パルプ工場はその後、閉鎖に追い込まれて更地となり、しばらくは私たち子供の遊び場だった。今は、大型スーパーに姿を変えている。江ノ口川は清流を取り戻し、魚も水草もよみがえった。私が大人になったころ、夏に帰省すると、川ではいつも子供たちが網を持ち、「ハヤ」と呼ばれる魚を追い回していた。
近所から「茶色」が消えるころ、全国各地の公害問題も鎮まった。環境問題に対する意識の高まりとか、環境保全技術の発達とか、要因はいろいろある。もっとも公害の発生源が、日本から主に東南アジア地域に移ったことは、案外、忘れられている。種々の工場が公害ごと外国に移転したというほど単純ではないものの、産業全体をみれば、あながち的外れな指摘ではない。
先進国は確かに、緑色と経済成長の双方を手に入れるようになってきた。それは、自らの利益のために、茶色であることを引き受けた国々、例えば、中国などが存在するからこそ、でもある。



 在留届は提出しましたか?
在留届は提出しましたか?